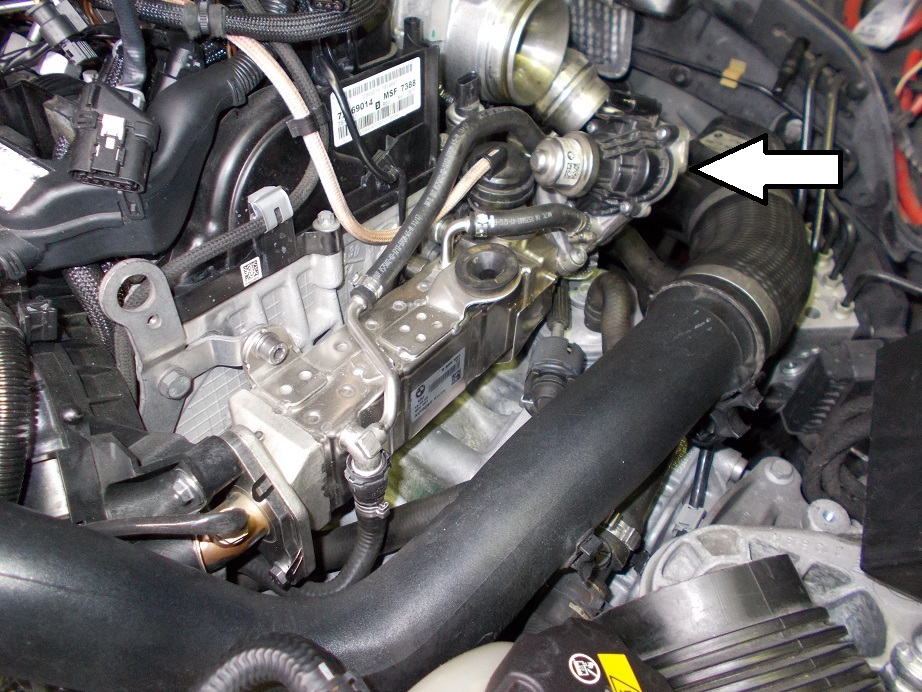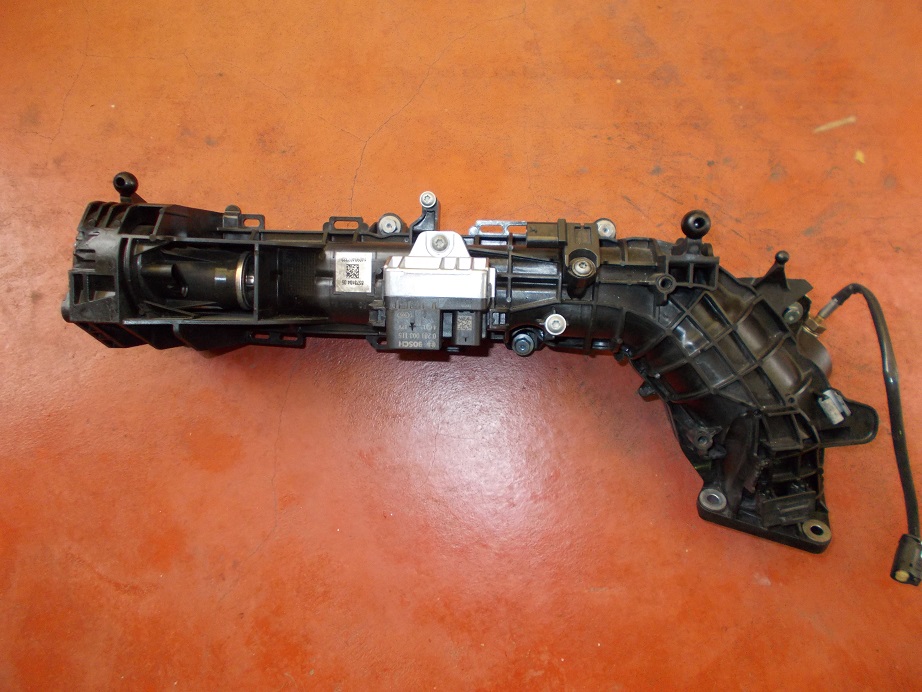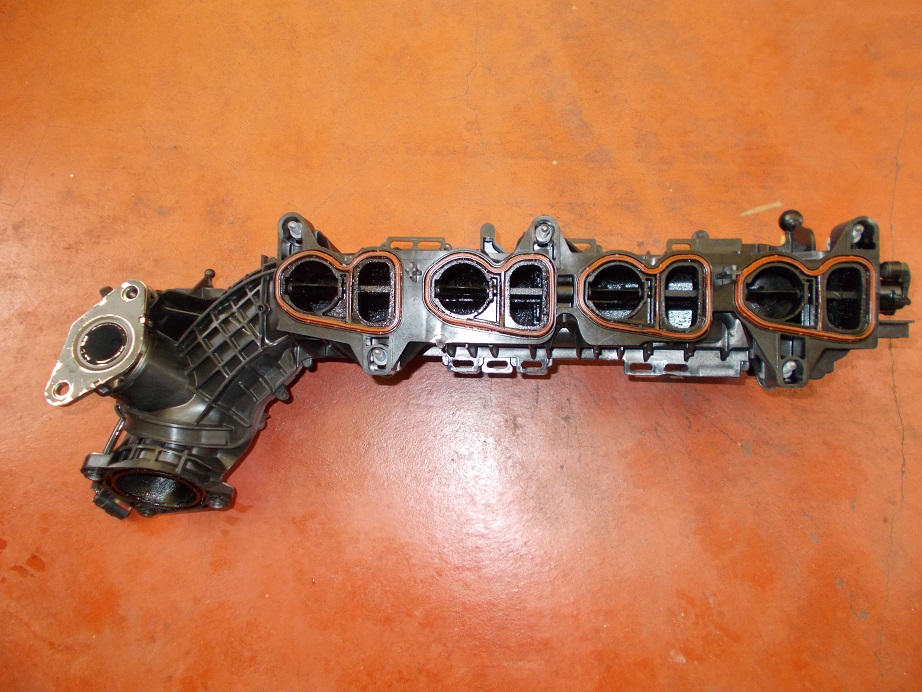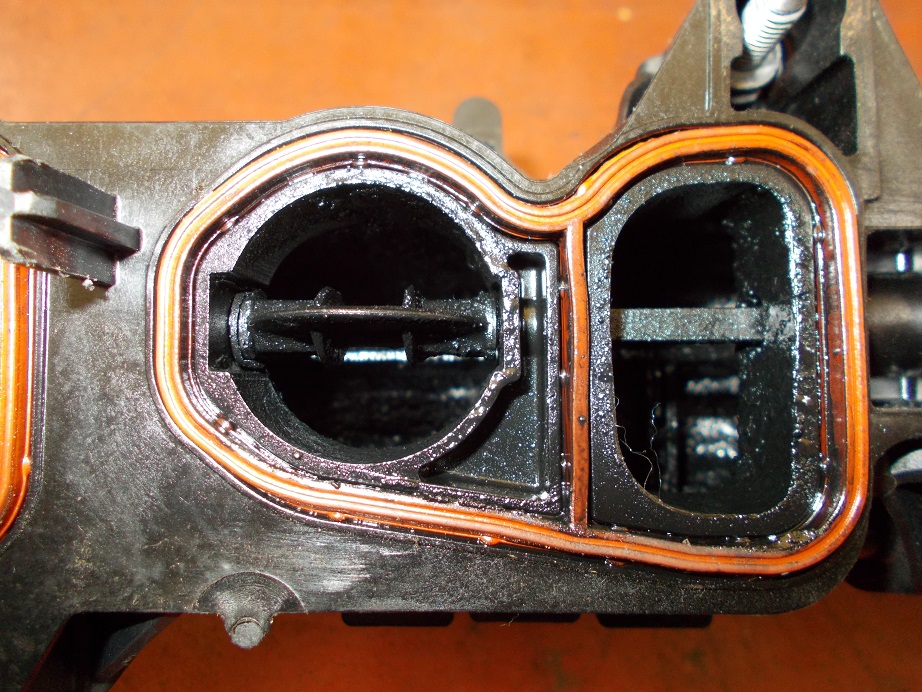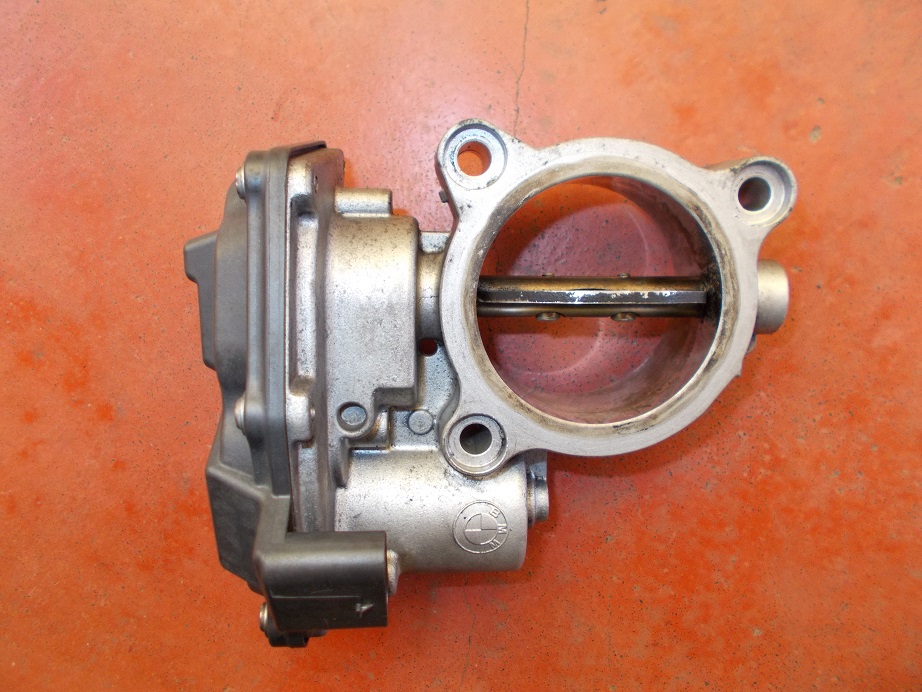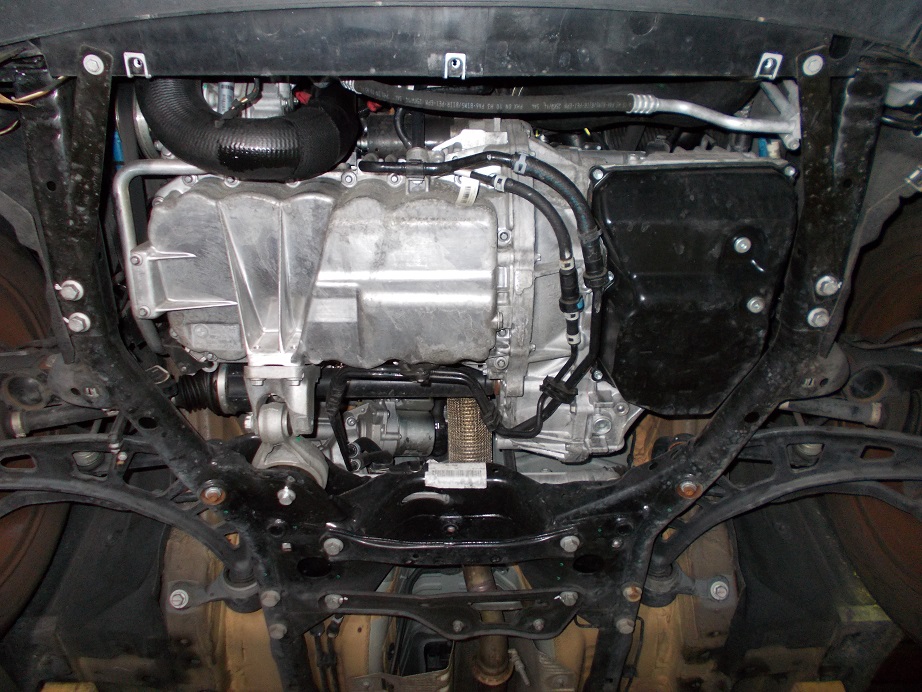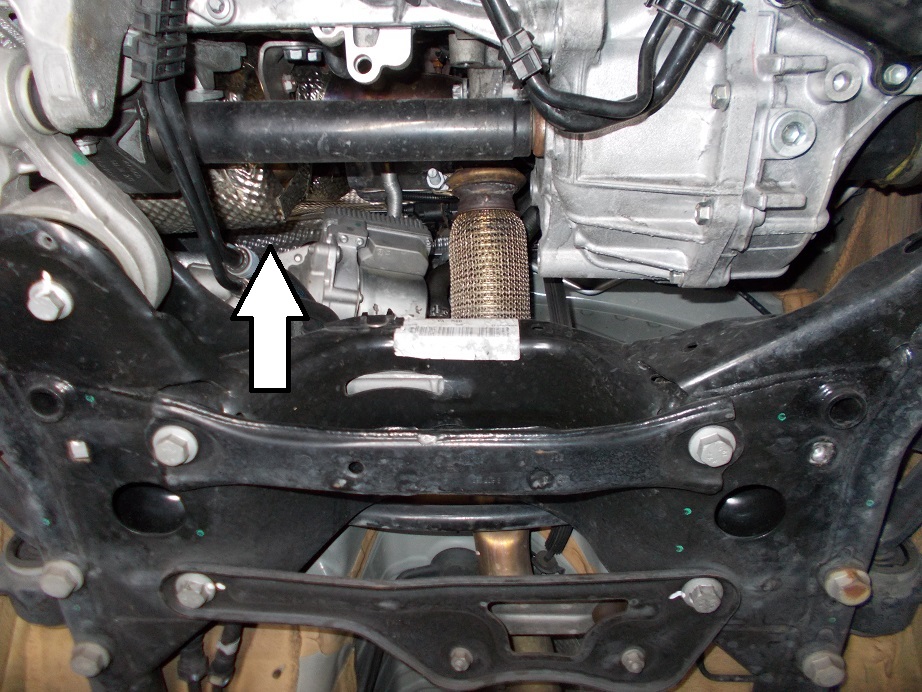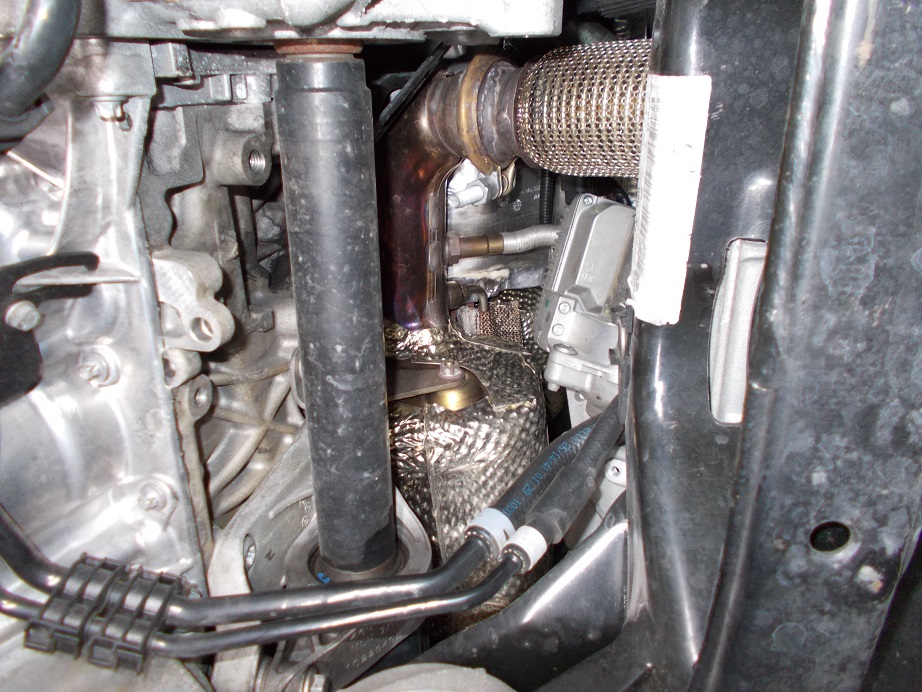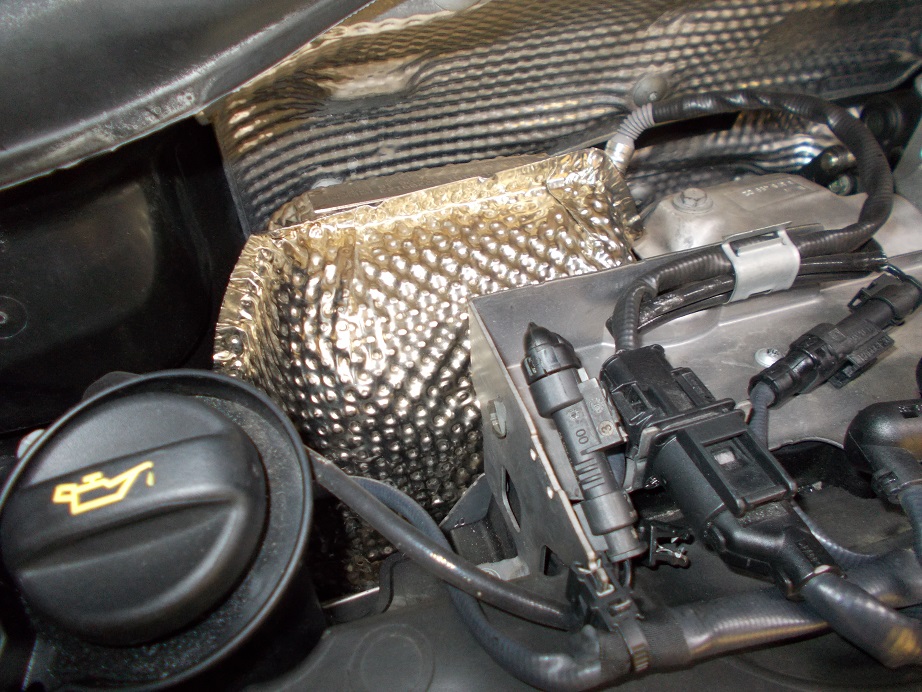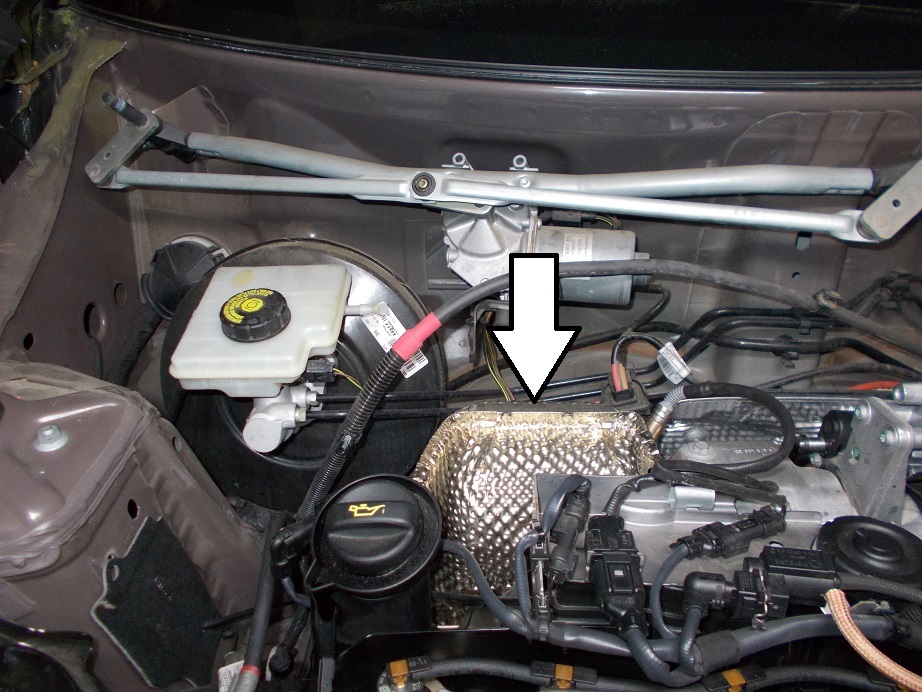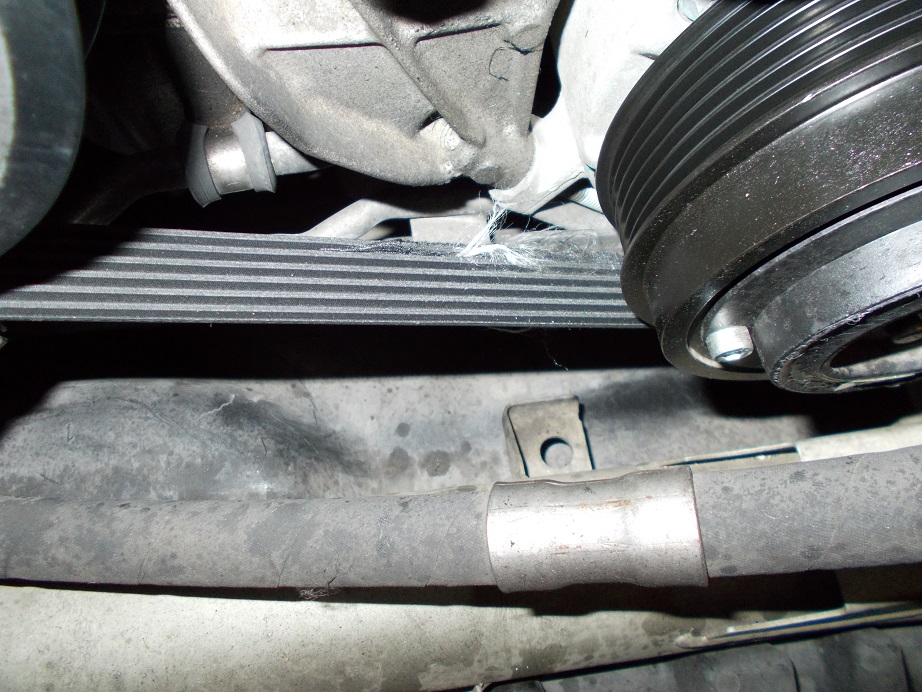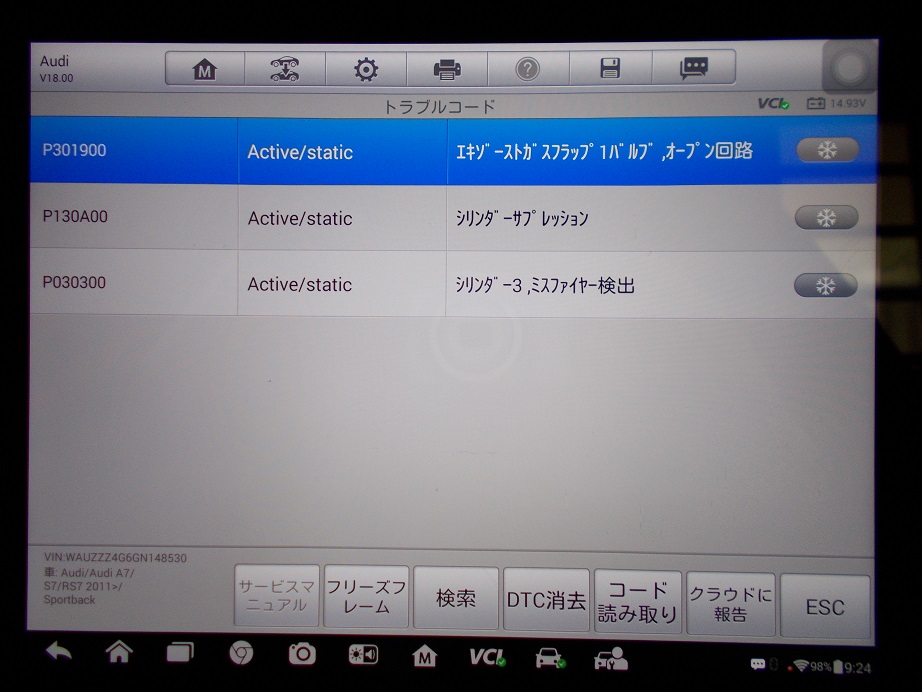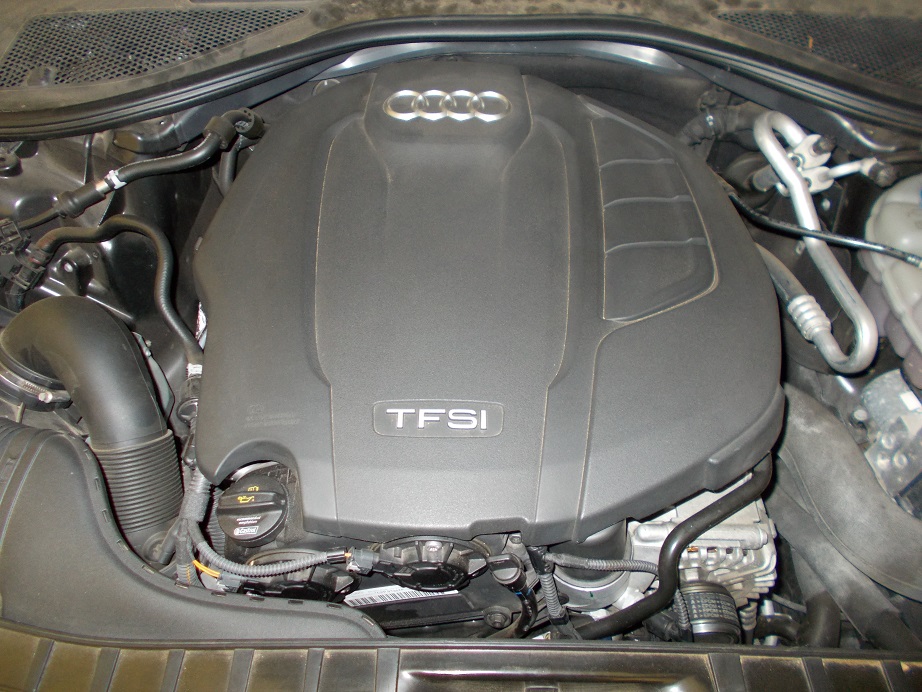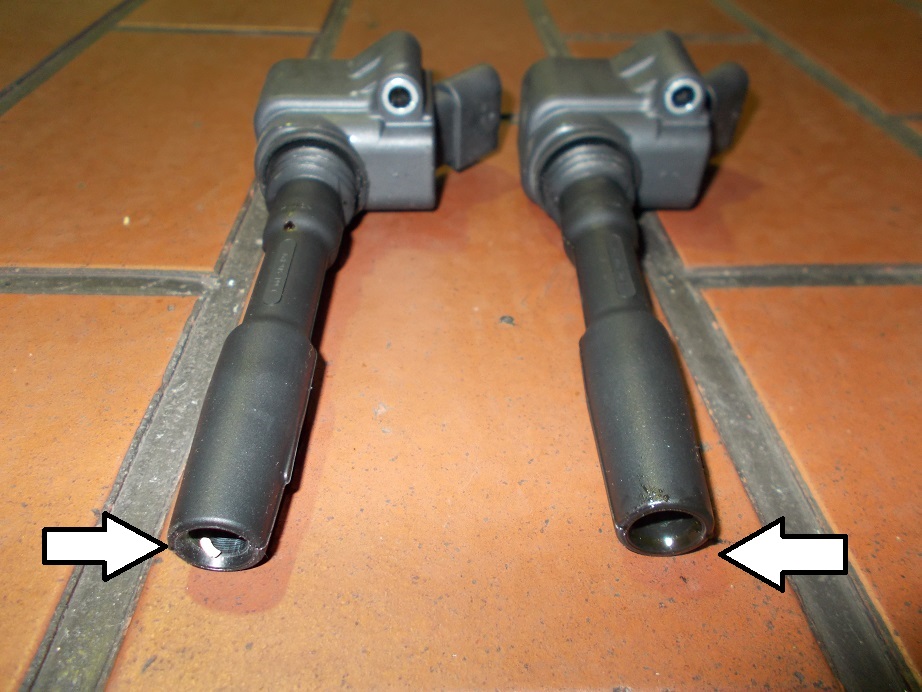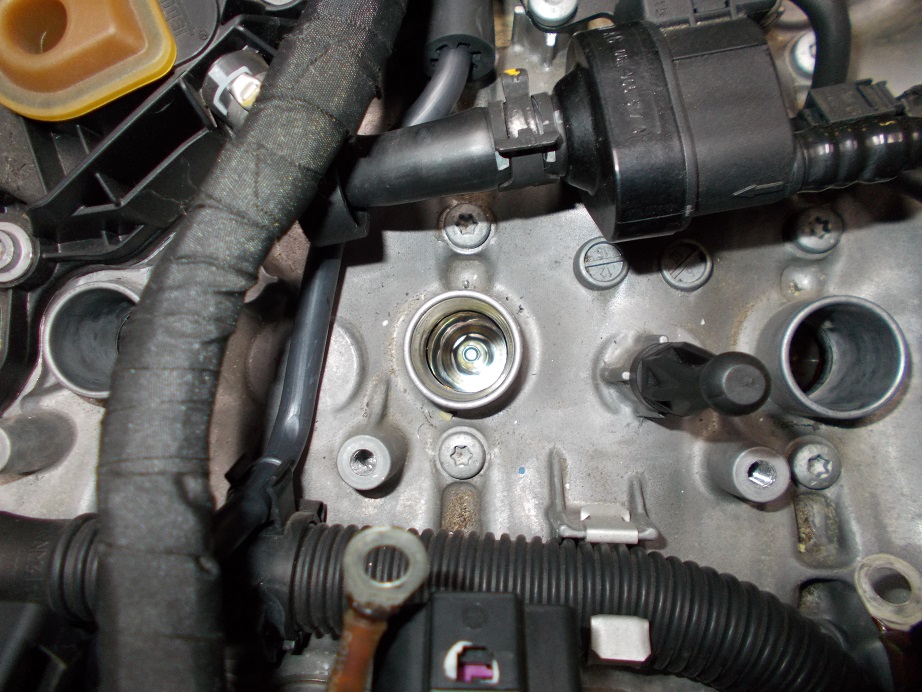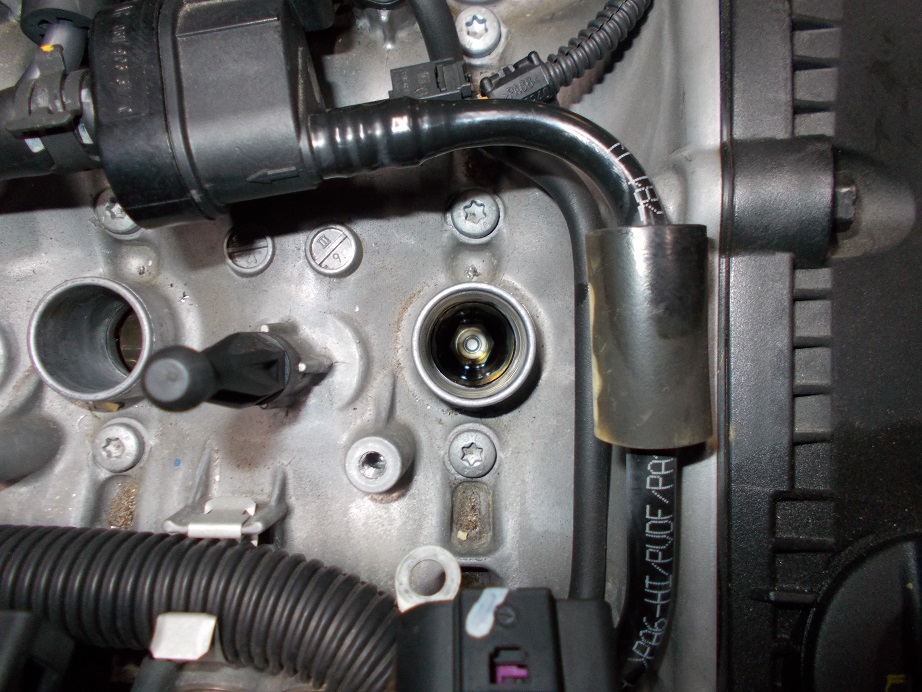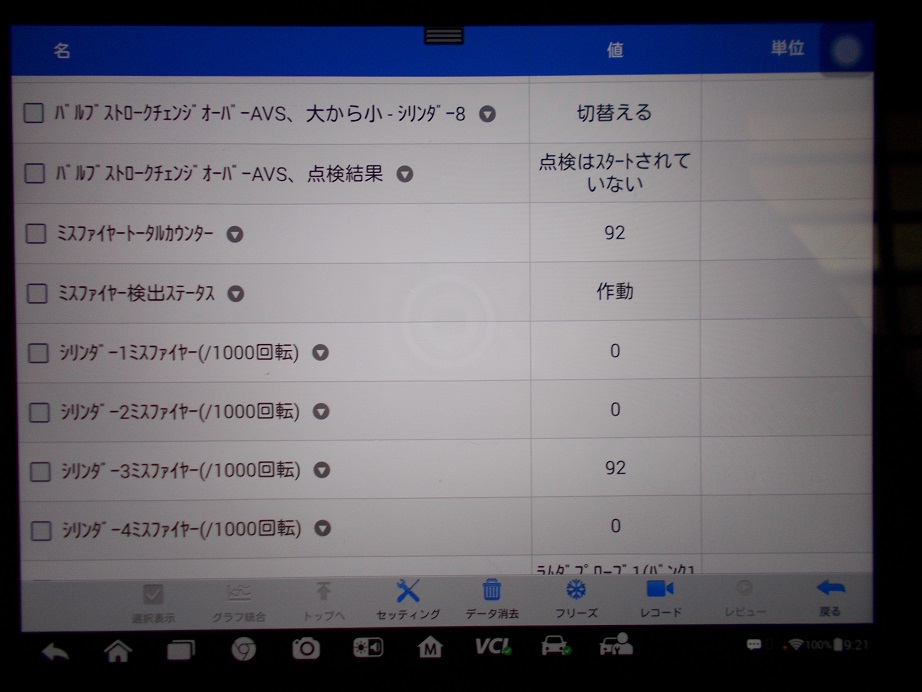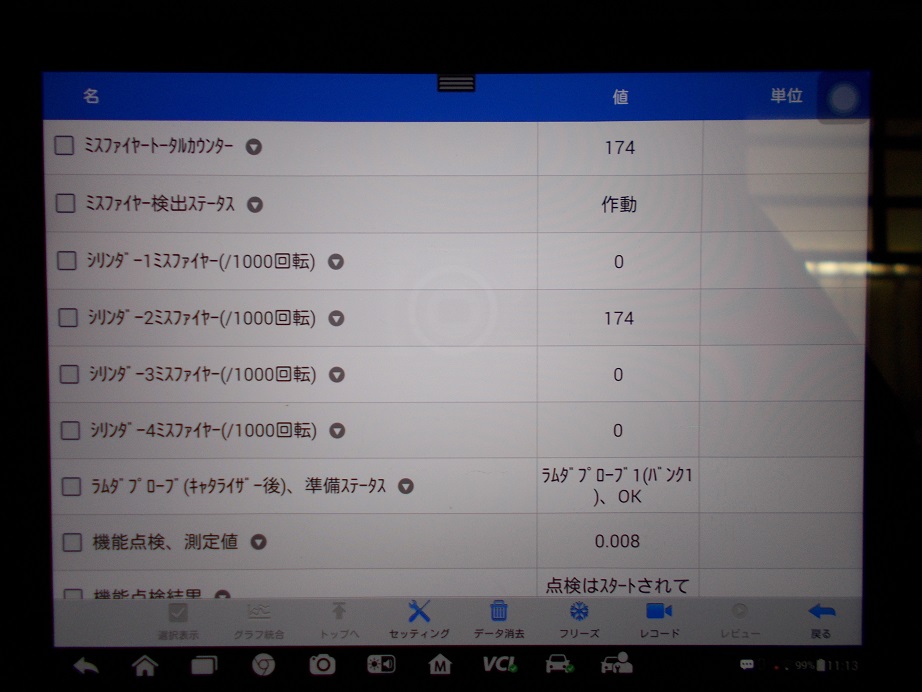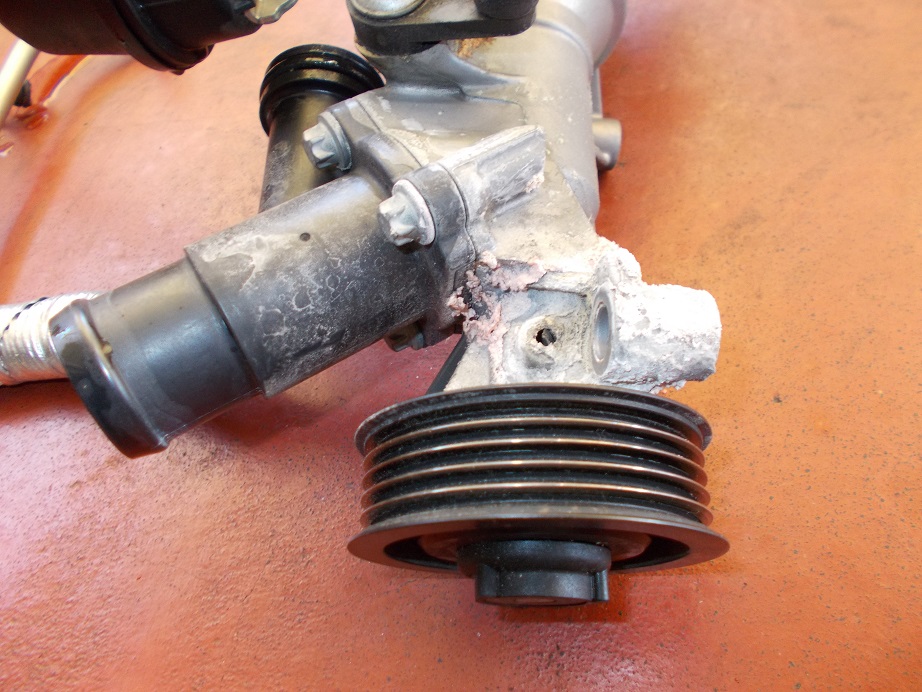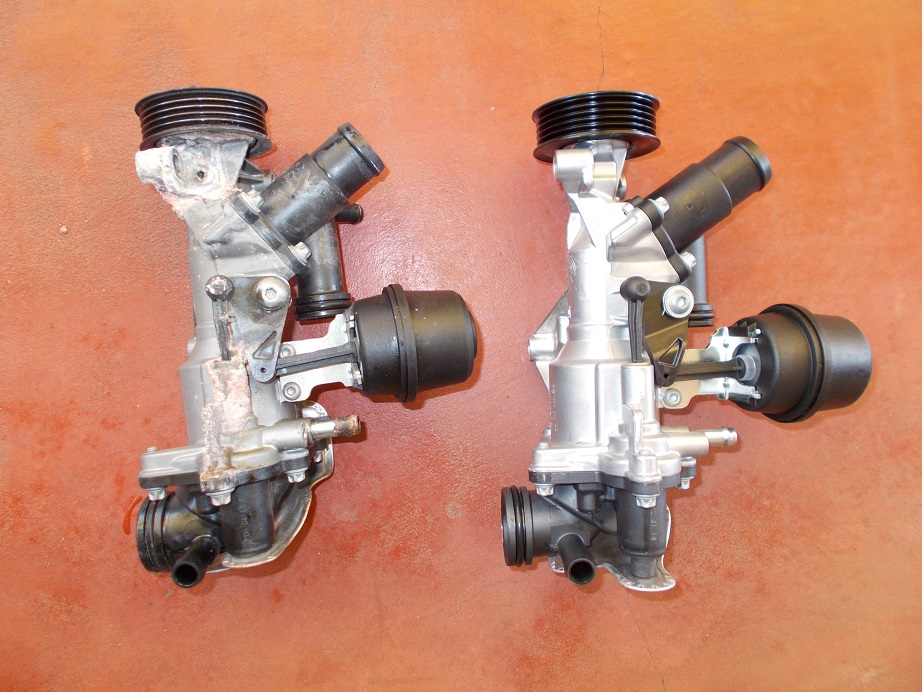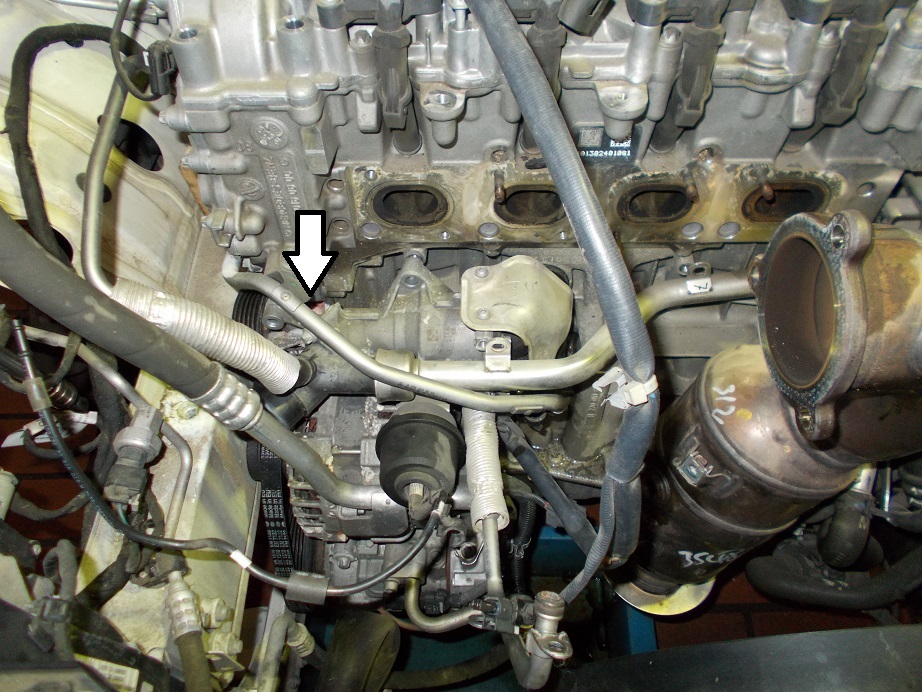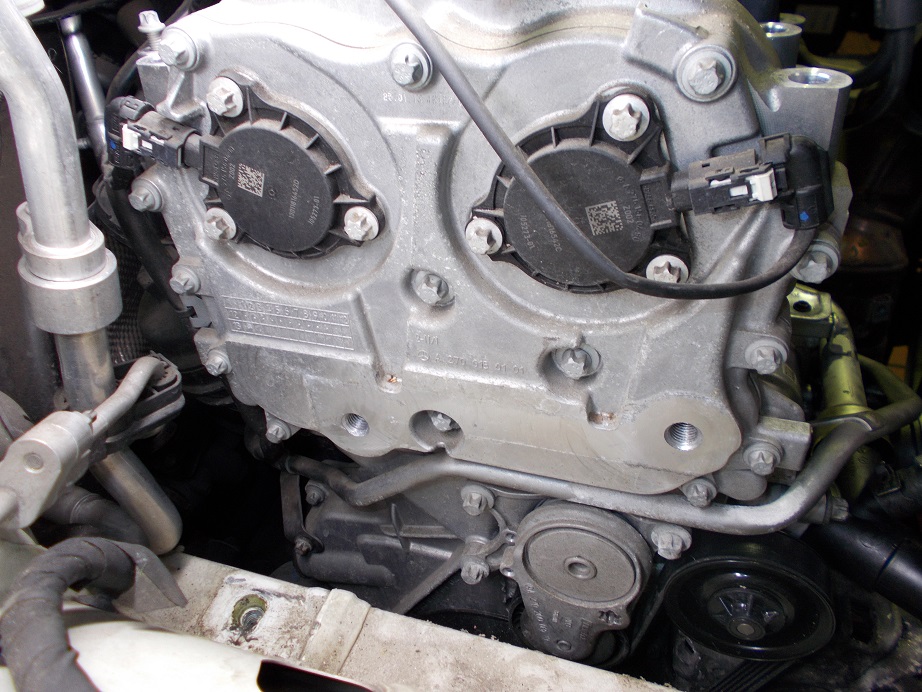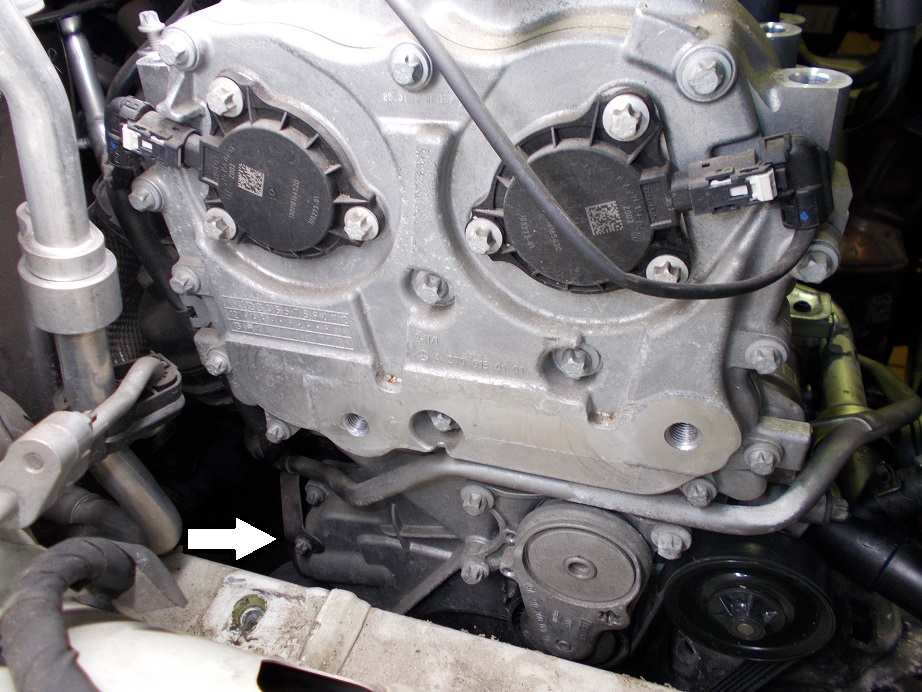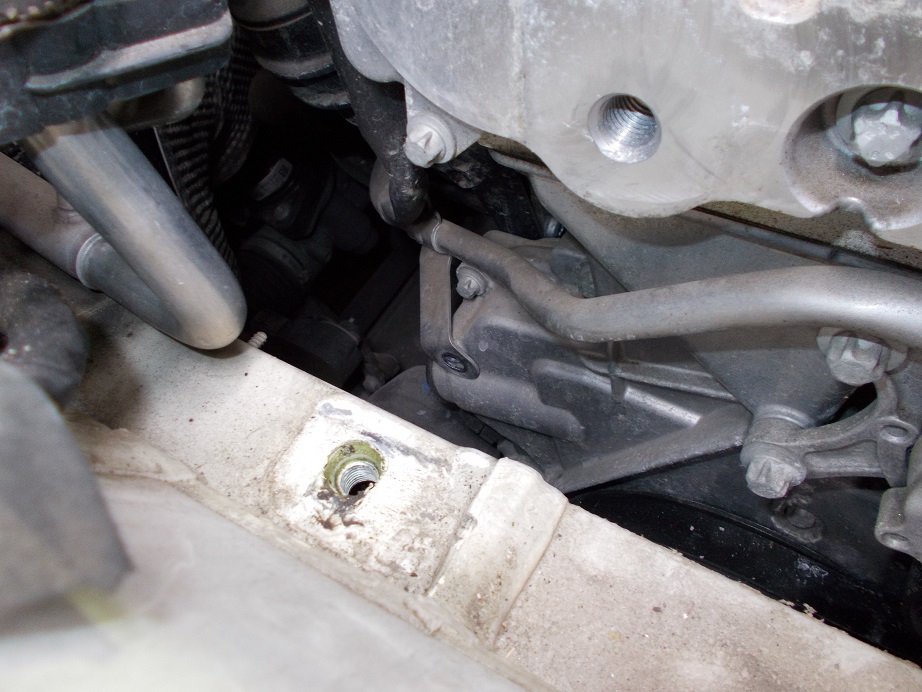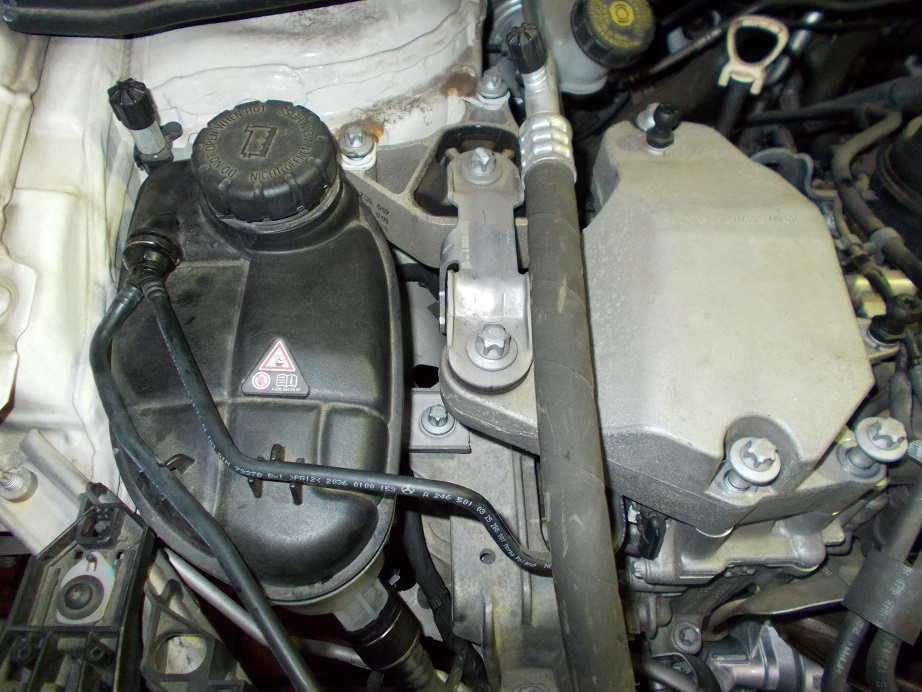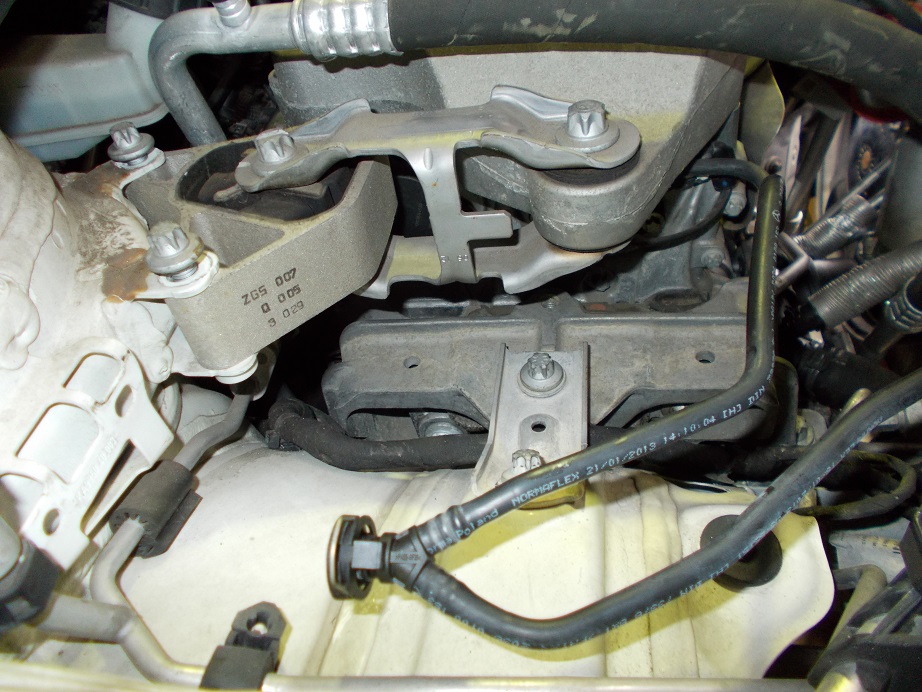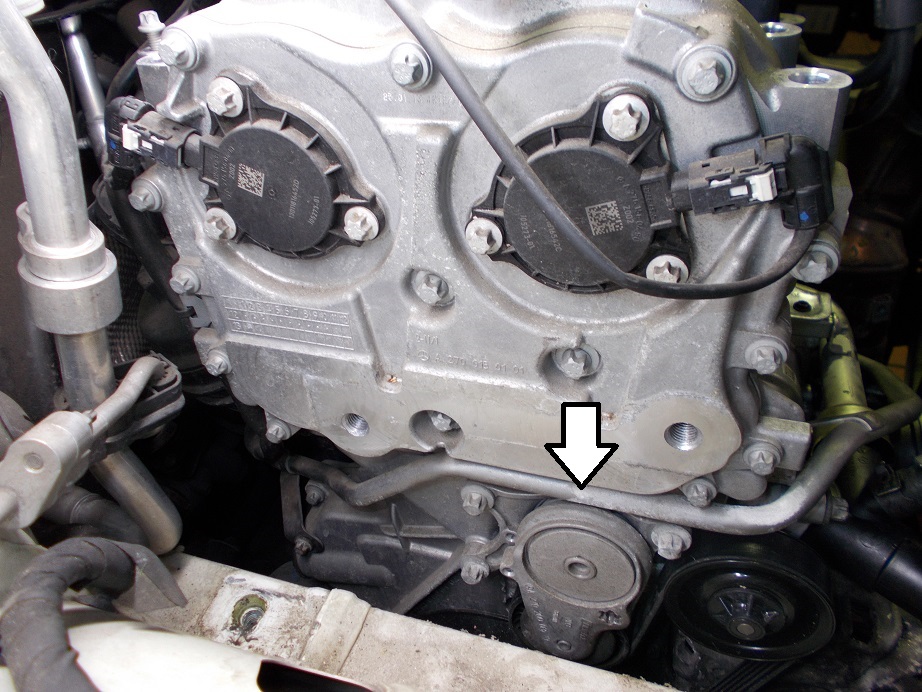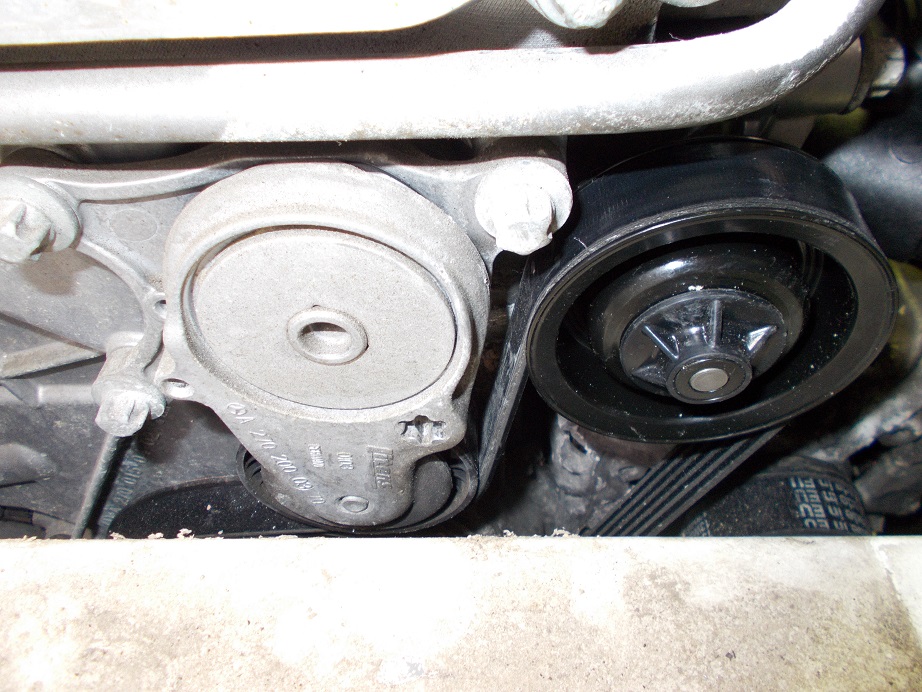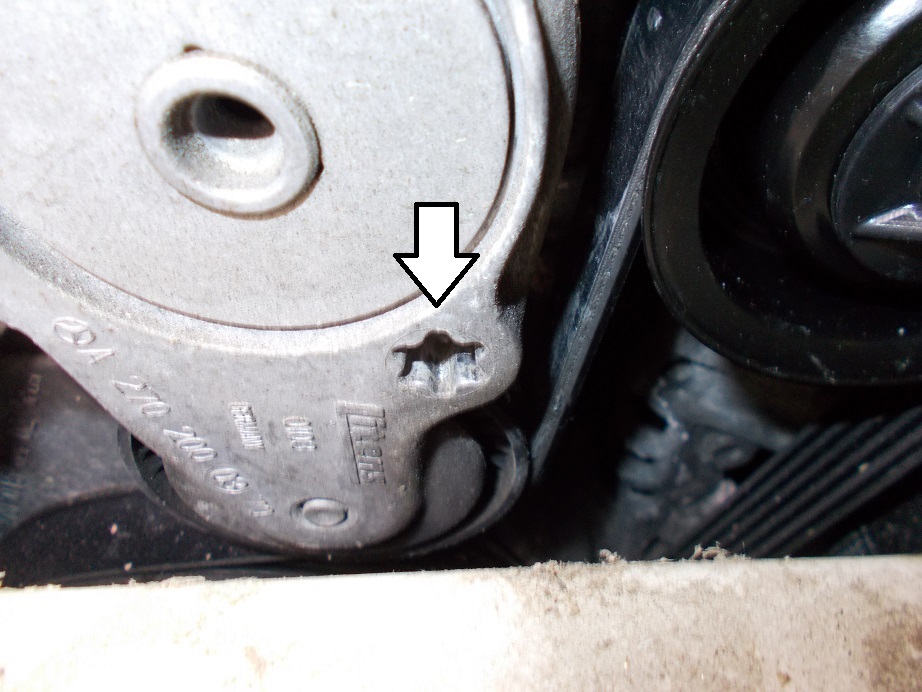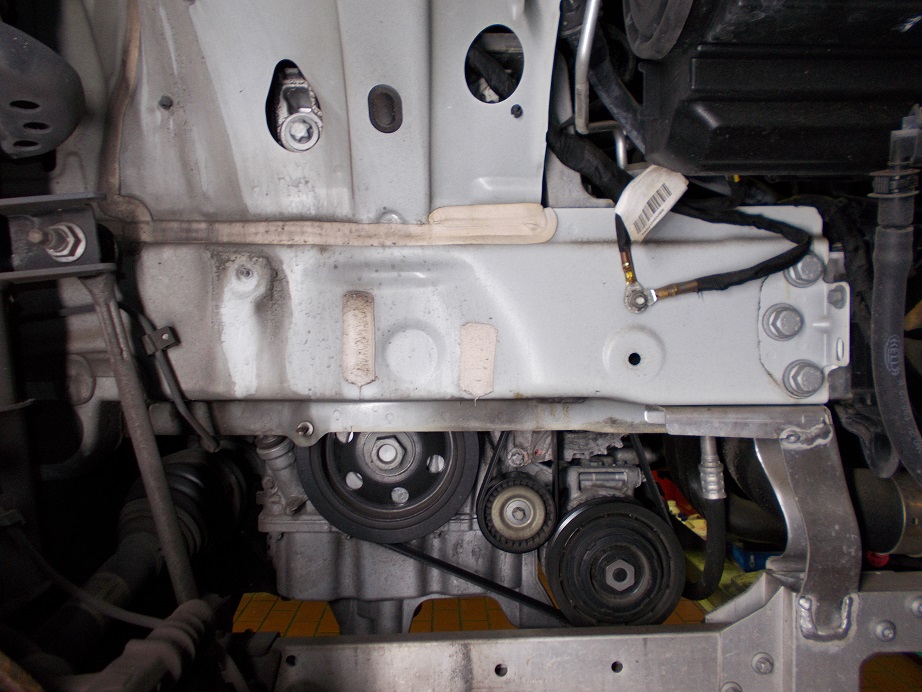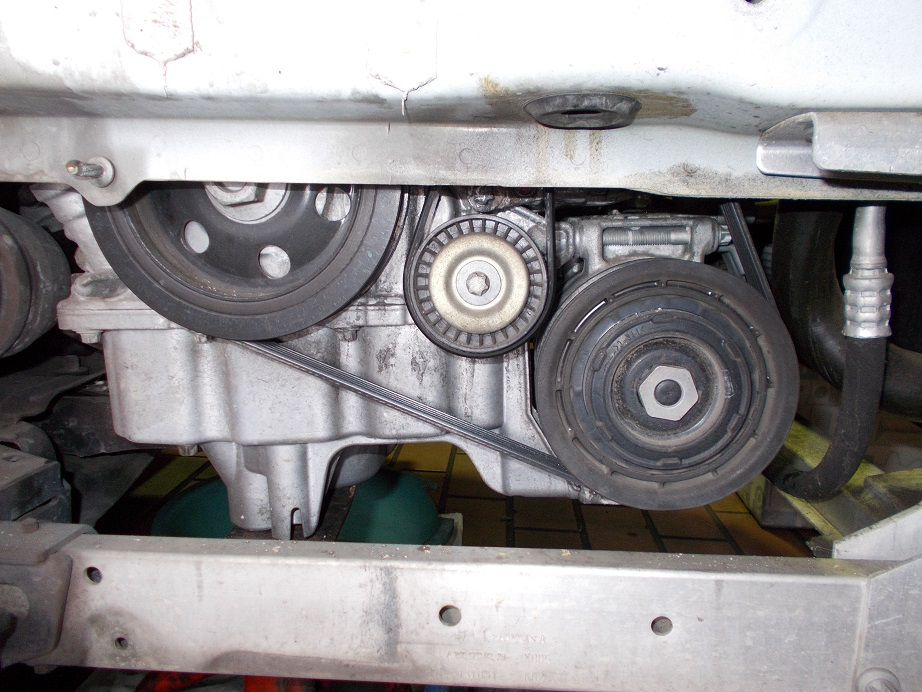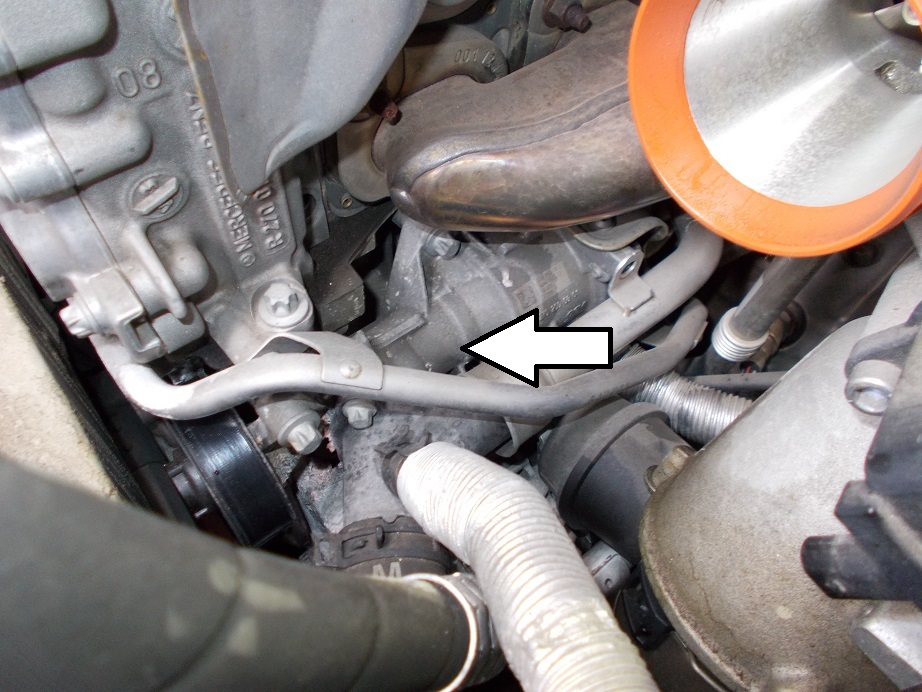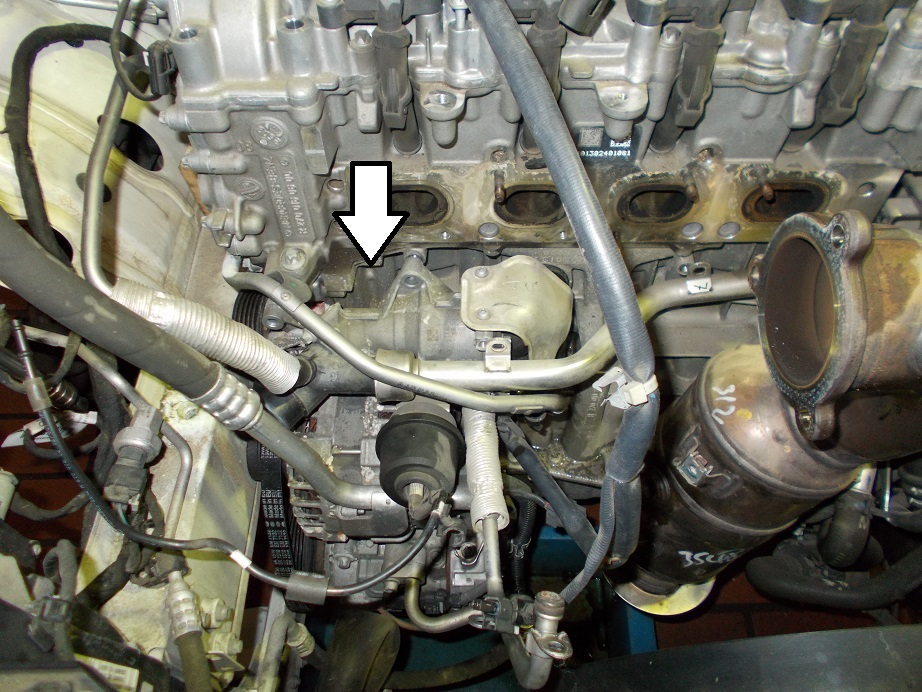前回の更に続きとなります。
こちらが取り外す事が出来た「パティキュレートフィルター」です。

最終的には、どうやって外せたかというと…
ディーラーさんが言っていた「上から取り外す」事は出来ませんでした(泣)
何故かというと、このフィルターの大きさから分かるように、そんな「スペース」ありません!
では、どうしたかというと…
答えはこちら↓↓↓

サブフレームと一緒にエンジン降ろしました(汗)
パティキュレートフィルターの状態がこちら↓↓↓
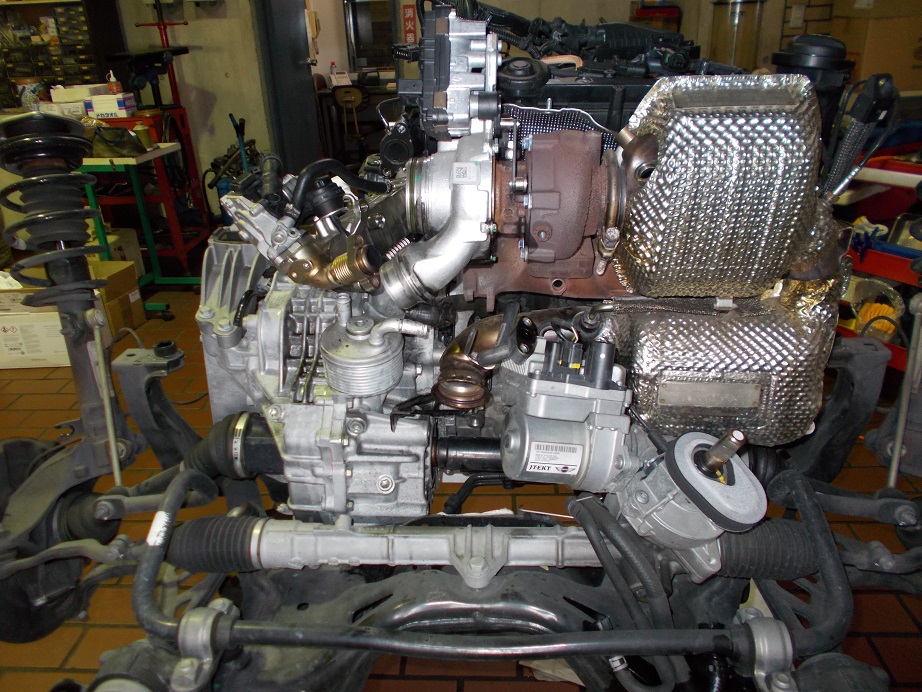
まず、ターボチャージャーが外れないんですよね(汗)
作業マニュアルにも、そう記載されてはいるんですが…
当然、この状態でエキゾーストマニホールドは外れませんので。
結果として、エンジン降ろさないとダメって事になった訳です。
パティキュレートフィルターが外れた状態がこちら↓↓↓
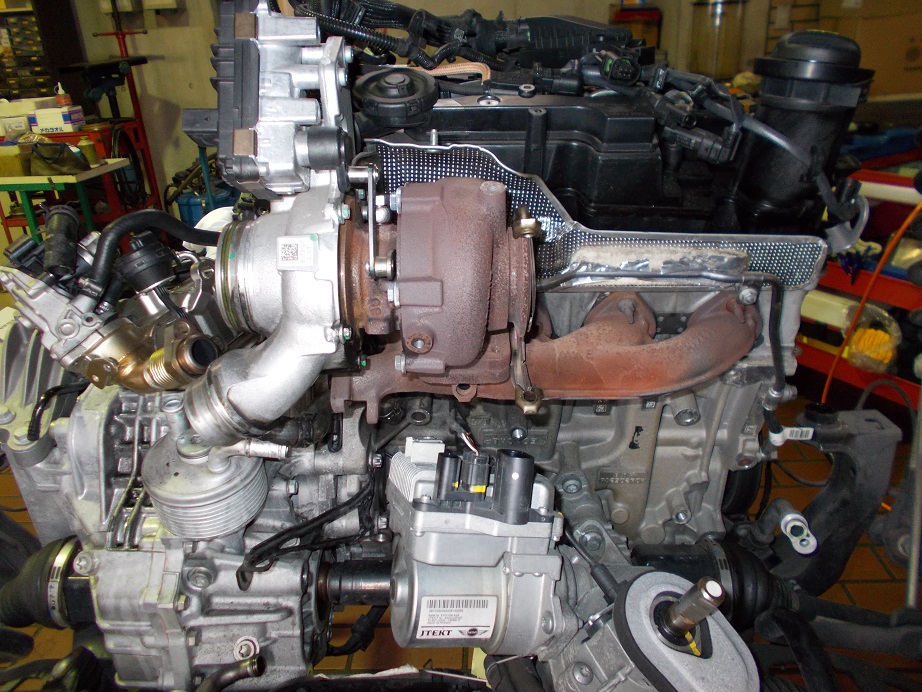
この状態でエンジンルームに戻すと、こうなります。
ドン!↓↓↓

これじゃ、パティキュレートフィルターが上から出てくる訳が無いですよね。

ちなみに上側の部分が触媒で、下側の部分がパティキュレートフィルターとなります。
裏返してみると分かりやすいでしょうか。
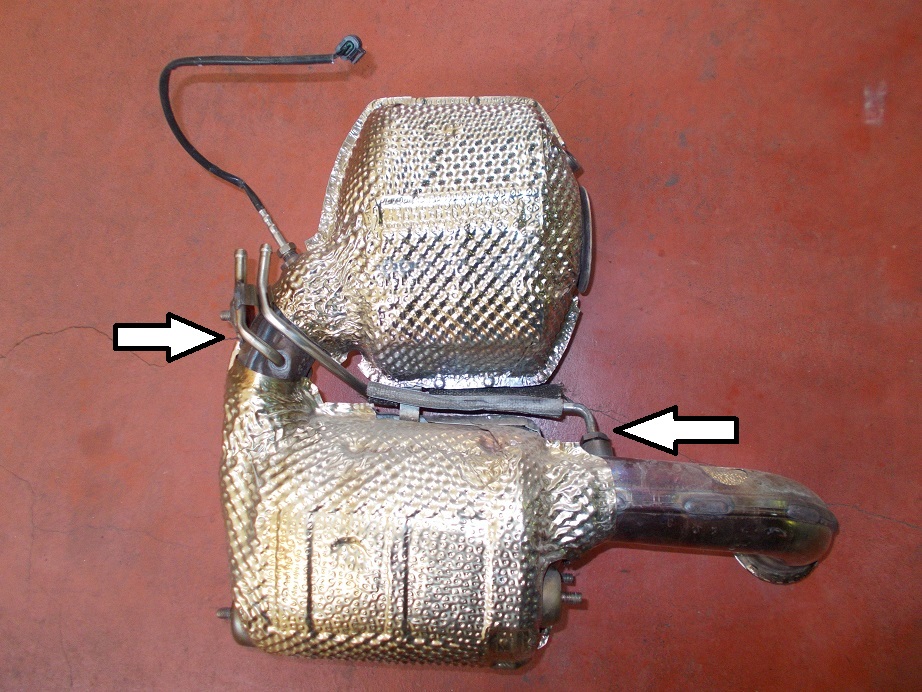
見ての通りですが、左側の矢印のパイプが入口側。
右側のパイプが出口側になっています。
両方のパイプの先にはプレッシャーセンサーが配置されていて、フィルター内部の詰まり具合を監視しています。
それに反応して、このような警告メッセージを点灯させるのです。

この後、取り外したパティキュレートフィルターは、修理してくれる業者さんへ。
パティキュレートフィルターが戻って来て、組み上げて完成です。
エンジン掛けた後↓↓↓

警告メッセージは点灯しなくなりました。
なかなか大変な作業でした。
ディーゼルエンジンを載っている方は、いつか必ず出会う修理です。
決して安くはない修理ですので。
ご覚悟下され~(汗)
※注意!
ここに掲載致しました、パティキュレートフィルター本体の修理に関しては、弊社が直接、依頼した訳ではないため、申し訳ございませんが、お問い合わせ頂いても回答は出来ません。
インターネットなどを活用して、お住まいに近い業者さんを探して頂き、直接ご相談下さい。